小6社会 政治経済総合演習プリント
1. 以下は2003年度の日本政府予算の歳出の内訳を示したグラフです。これについて、各問に答えなさい。
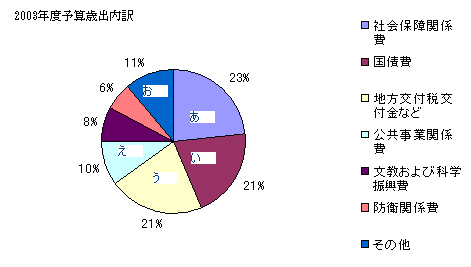
問1 グラフの「あ」の部分に関連して
① この項目は、日本国憲法に規定されているある基本的人権に基づくものです。その権利とは何か。
② この項目について、正しく説明した文を以下から選びなさい
ア.主に国内で発生した自然災害の復旧費用に充てられ、国土交通省の業務に深く関係する予算である。
イ.主に文部科学省の業務に深く関係する予算で、今後少子化が進むため減少することが予想される。
ウ.主に厚生労働省の業務に深く関係する予算で、今後高齢化が進むため増加することが予想される。
エ.主に社会福祉の費用に充てられ、経済産業省の業務に深く関係する予算である。
問2 グラフの「い」の項目に関連して
① これは何のための費用に充てられるか
② この項目は今後増加すると予想されるか、それとも減少すると予想されるか。
問3 グラフの「う」の項目の交付先として誤っているものを以下から選びなさい。
ア.
問4 グラフの「え」の項目について、誤って述べたものを以下から選びなさい。
ア.主に高速道路や空港、港湾の整備の費用に充てられる予算である。
イ.不況の際には増加する傾向があり、ここ5年間増加し続けている。
ウ.主に国土交通省や農林水産省の業務に深く関わる予算である。
エ.巨額の費用のかかる計画が多いため、近年見直しが進んでいる。
問5 グラフの「お」の項目には、日本政府から発展途上国への資金援助費用が含まれています。この費用のことを何というかアルファベット3文字で答えなさい。
問6 日本の政府予算の歳出総額はおおよそどれくらいですか。
ア.60兆円 イ.70兆円 ウ.80兆円 エ.100兆円
2. 以下は、日本の政治と法の関係について述べた文章です。これについて、各問に答えなさい。
私たちが集団で生活するためには、一定のルールが必要です。国家が大きな集団である以上、(1)国家の方針を決める政治を行うために、国家のルールとしての法律が必要とされるのはいうまでもありません。政治とは何かについて、法律を通じて考えてみましょう。
普段、私たちが物事を行うときには「計画」を立て、それを「実行」し、その結果を後から「振り返る」という3段階の仕組みをとります。同じように、政治も(2)法律を「作り」、「適用(実行)し」、その適用の仕方が正しかったかどうかを「判断する」という3つの段階から行われています。日本の政治では、この3つの働きをそれぞれ別の機関に担当させ、(3)お互いに行き過ぎが生じないようチェックさせるという仕組みをとっています。
まず法律を「作る」ということですが、そのためにはその法律を定める目的が明確でなければなりません。すべての法律が目指すべきおおもとの目標を定めたもの、それが「法律の法律」、つまり憲法になります。日本最古の憲法は(4)十七条憲法とされていますが、これは役人の心構えを定めたものであり、今述べた意味での憲法にはそぐわないものと言えるでしょう。その後も、中国の唐にならって(5)刑罰のルールや政治のルールを定めた法律が作られたり、(6)武家による法律が定められたりしたことはありましたが、すべての法律が従うべき「基本となる法律」としての憲法が定められるのは(7)ずっと後のことになります。
さて、法律を「作る」のは、憲法の(8)ある原則から、国民に選挙された代表者で構成される(9)国会の仕事であるとされています。しかし、実際は純粋に法律案の作成段階から国会議員だけで作られた法律は数が少なく、(10)国会で成立した法律の大半は、もとの法律案を国民に選挙されない官僚が作成しているという問題があります。
法律を「実行する」のは内閣の仕事です。現在、内閣は(11)1府12省庁から成っており、国会で作られた法律に従って、より具体的に(12)内閣が定めるルールや各省庁の定める省令・規則などを適用しながら政治を行っています。また、予算案の作成や予算の執行、(13)外国や国際機関との交渉なども内閣の重要な仕事です。日本では(14)国会と内閣が密接に結びついて政治を行う仕組みがとられていますが、省庁のトップである閣僚が短期間で交代しがちで政策を実行するための政治家のリーダーシップが発揮されにくい、また、政策の決定までに「族議員」と呼ばれる政治家がかかわり、国民にわかりにくい政治の仕組みになっているなどの課題を抱えています。
最後に法律を「判断する」のが裁判所の仕事です。裁判所は、通常(15)大きく2種類に分けられる裁判を行うほか、内閣の定めるルールや法律そのものが(16)憲法に違反していないかどうかの判断も担当します。このため裁判の公平性を保つために、国民は同じ内容について(17)最大で3回まで裁判を受けることができるほか、(18)裁判官は己の良心にのみ従うと憲法に明記されてい。また、最高裁判所の裁判官を定期的にチェックする仕組みとして(19)総選挙と同時に実施される制度がありますが、こちらは有効に活用されていないのが現状です。
日本国憲法の三大原理に(20)「基本的人権の尊重」が挙げられているように、人間に生まれつき備わっている権利を守ることが、現代政治の基本となっています。そのため、今ある制度上の課題に国民がより深く関わっていくことが、今後の民主政治の課題といえます。
問1 下線部(1)のような、国家の政治方針を決める究極の力のことを何というか。
問2 下線部(2)のような3つの働きをそれぞれ何というか。
問3 下線部(3)のような考えが述べられた本は何か、またその著者は誰か。
問4 下線部(4)に関連して、当時起こった政治的事件について正しく時代順に並べたものを以下から選びなさい。
ア.大化の改新→十七条憲法→遣隋使派遣→冠位十二階
イ.冠位十二階→遣隋使派遣→大化の改新→憲法十七条
ウ.冠位十二階→憲法十七条→遣隋使派遣→大化の改新
エ.憲法十七条→冠位十二階→遣隋使派遣→大化の改新
問5 下線部(5)に関連して
① それぞれ何というか
② 701年に藤原不比等らによって定められた本格的な法律を何というか。
問6 下線部(6)に関連して、武家の法律について、正しく述べた文を以下から選びなさい。
ア.豊臣秀吉は刀狩令を出し、石山本願寺の一向一揆を鎮圧した。
イ.北条泰時は1221年に武家初の法律である御成敗式目を制定した。
ウ.徳川家光は武家諸法度を強化し、新たに参勤交代の制を付け加えた。
エ.松平定信の出した寛政異学の禁に違反したため、吉田松陰らが処罰された。
問7 下線部(7)に関連して
① 明治時代、政府に近代憲法の制定を求めた運動を何というか。
② 明治時代に制定された憲法について、誤って述べた文を以下から選びなさい。
ア.この憲法の草案は、1885年に初代内閣総理大臣となった伊藤博文らによって作成された。
イ.主権は天皇にあったが、国民の基本的人権についても、不可侵のものとされた。
ウ.国民の三大義務は、勤労の義務、納税の義務、徴兵の義務だった。
エ.この憲法はドイツ憲法をモデルとしたが社会権については明記されなかった。
問8 下線部(8)の原則とは何ですか。
問9 下線部(9)に関連して、国会の仕事でないものを以下から選びなさい。
ア.内閣不信任決議 イ.弾劾裁判所の設置 ウ.天皇の国事行為に対する助言と承認 エ.国政調査権
問10 下線部(10)に関連して、法律が成立するまでの流れを正しく述べたものを以下から選びなさい。
ア.法律の成立には、必ず衆、参議院の両院での過半数の賛成による可決が必要である。
イ.法律案の審議は、必ず衆議院から行われなければならない。
ウ.憲法の改正も、通常の法律案審議と同じ流れで国会の議決で決定できる。
エ.両院協議会を開いても両院の意見が異なる場合、衆議院の3分の2以上の賛成で法律は成立する。
問11 下線部(11)に関連して、次の業務を行うのはどの省庁か。
ア.農協から仕入れた米を消費者に安く売る イ.H2ロケットを打ち上げる
ウ.東北新幹線の八戸までの延伸を認める エ.外国との条約を締結する
問12 下線部(12)のことを何といいますか
問13 下線部(13)に関連して、外国との間で結ぶ約束のことを何といいますか。またこの約束を承認する機関は
何ですか
問14 下線部(14)に関連して
① このような仕組みを何といいますか
② このような仕組みを改めて、アメリカ大統領のような強力なリーダーシップを発揮できるよう、国民が首相を直接選べる仕組み(首相公選制)に変えるとしたら、法律上ではどんな作業が必要ですか。
問15 下線部(15)の2種類の裁判とはそれぞれ何ですか。
問16 下線部(16)のような権限を何といいますか。
問17 下線部(17)の仕組みについて正しく述べた文を以下から選びなさい。
ア.例えば地方裁判所で2回など、同じ裁判所で複数回裁判を受けられる。
イ.一度最高裁判所で裁判を行った場合でも、回数が3回未満ならば、下級裁判所で裁判を受けられる。
ウ.家庭裁判所や簡易裁判所で判決を受けたら、次は地方裁判所以上の裁判所で裁判しなければならない。
エ.憲法に違反しているかどうかの判断は、裁判の回数に関わりなく最高裁判所でしか下せない。
問18 下線部(18)のことを何といいますか。また、このことを守ったとされる明治時代の事件を答えなさい。
問19 下線部(19)のような制度を何といいますか。
問20 下線部(20)について、基本的人権を大きく4種類に分けたとき、以下はどの権利に属しますか。
ア.小学校へ授業を受けに行く イ.新聞に自分の意見を発表する
ウ.損害賠償を求めて裁判をおこす エ.身分制度を廃止する
3. 以下は、日本経済の課題について述べた文章です。これについて、各問に答えなさい。
日本の経済は、1973年の(1)オイルショック以降、いわゆる低成長時代に入り大きく様変わりしてきました。特に、円高の進行とともに、激化する(2)貿易摩擦の影響で、(3)生産工場を貿易相手国に移す企業が増えると同時に、外国企業との競争に勝つために、賃金の安い東南アジアに工場を移す動きも増えました。この結果、現在日本国内では、各地で大きな工場跡地をどのように活用するのかを真剣に検討する地方自治体が増えています。例えば、工場跡地にショッピングスーパーを誘致するなどといった事例が見られます。
しかし、このような生産の海外流出とともに、もう一つの大きな課題を日本経済は抱えています。それは少子高齢化の進展により、将来的に働き手が減少して産業が衰退するとともに、(4)年金などの社会保障の費用をまかないきれなくなるのではないかという不安です。
これらの課題を解決するために、第1に、国の借金を減らすために、(5)無駄な歳出を減らし、将来の財政負担を軽くするとともに、第2に、(6)様々な規制を緩和して新しい産業が育つ土台をつくることが必要です。しかし、これらの改革はまだ始まったばかりであることに加え、予測される働き手の減少に対する根本的な対応策は取られていないのが現状で、今後は本格的な(7)少子化対策が望まれることになります。
問1 下線部(1)について
① この事件のきっかけとなった戦争は何か
② この時、原油の値上げを決めた機関名をアルファベット4文字で答えなさい。
問2 下線部(2)について、1960年代に鉄鋼の輸出をめぐる貿易摩擦が起きたときの、日本側の対応策は何か。
問3 下線部(3)について
① このことを何というか
② このことについて誤って説明した文を以下から選びなさい
ア.相手国の労働者を雇用することができるので、貿易摩擦の解消につながる
イ.工場の跡地に大きな団地ができたので、住宅不足が解消された。
ウ.国内では産業の空洞化により、税収不足に悩む地方自治体が増えた。
エ.為替変動による損失を回避できる利点がある。
問4 下線部(4)について正しく述べた文を以下から選びなさい。
ア.費用は全額、消費税などの税金でまかなわれている
イ.最近新たに介護保険制度がスタートしたが、高齢者は保険料を負担していない。
ウ.通院、入院などの医療費もこの費用に含まれている。
エ.生命保険、損害保険などの費用も含まれている。
問5 下線部(5)について、ふさわしくないものを以下から選びなさい。
ア.年金の支給開始年齢の引き上げ イ.地方自治体への補助金削減
ウ.警察官、教員人数の増加 エ.巨大ダム工事の中止
問6 下線部(6)について、ふさわしくないものを以下から選びなさい。
ア.コンビニで、健康ドリンク剤が買えるようになった。
イ.近所の駐車場跡地に大きなスーパーができた。
ウ.スーパーで売られている野菜のすべてに、生産地の表示がされるようになった。
エ.同じ距離を走っても、タクシー会社によって運賃が違う
問7 下線部(7)について、ふさわしくないものを以下から選びなさい。
ア.保育所をたくさん作る イ.育児休暇をとりやすくする
ウ.子どものいる世帯への援助額を増やす エ.男女雇用機会均等法の制定
4. 以下は戦後の日本の経済の歴史について説明した文です。これについてあとの問に答えなさい。
第二次世界大戦後の日本は、憲法に定められた平和主義の原則にしたがい、防衛費を低く抑えその分、国力を経済発展に注ぐというスタイルで復興して来ました。特に、1950年の(1)朝鮮戦争をきっかけに始まった好景気は、その後1960年に発表された(2)所得倍増計画のもと、(3)高度経済成長といわれるめざましい発達へとつながり、日本が先進国の仲間入りをする土台を築き上げたのでした。
しかし、1973年に発生したオイルショック以降の低成長時代では、1980年代後半のバブル景気を最後に、日本はその後「失われた10年間」と呼ばれる(4)長い不景気の時代に突入しました。この10年間の間、政府は様々な対策を行いましたが、景気はなかなか良くならず、(5)企業の倒産や(6)失業者が増加するといった問題が生じました。そこで、2001年に登場した小泉内閣では銀行の(7)不良債権処理を進めるとともに、「構造改革」と呼ばれる様々な改革にとりかかりました。
問1 この好景気を「特需景気」といいます。この後、1950年代は「神武景気」、「岩戸景気」と立て続けに好景気の時代が続きます。このことについて
① 好景気のとき、物価はどうなりますか。またこの物価変動を何といいますか。カタカナで答えなさい
② ①のとき、日本銀行は公定歩合をどうしますか
問2 この計画の目標は、経済水準の指標である「国民総生産(GNP)」を10年間で2倍に増やすことでした。では現在「GNP」に替わる指標になっているものを何といいますか。アルファベットで答えなさい。
問3 当時、1964年の東京オリンピックにあわせて開通した日本初の高速道路と新幹線を何といいますか。
問4 不景気のときに政府や日本銀行がとる政策として誤っているものを以下から選びなさい。
ア.日銀が資金を銀行に貸し出す時の金利である公定歩合を引き下げる。
イ.企業が経済活動を行いやすくするために、様々な規制をゆるめたり廃止したりする。
ウ.増税を行い、政府が様々な事業を行いやすくする。
エ.ダムや空港、高速道路建設などの公共事業を増やす。
問5 企業について
①日本の企業のなかで最も数が多いのは以下のどれか
ア.有限会社 イ.合資会社 ウ.株式会社 エ.合名会社
②企業の行う経済活動の説明として誤っているものを以下から選びなさい
ア.利益を上げることを目的としており、モノやサービスなどの商品を提供する供給者である。
イ.商品の生産に必要な労働力は家計から提供される。
ウ.商品の生産に必要な資金は、商品の代金のほか金融機関からの借金や株式の発行で集めている。
エ.株式を買った株主には、利益のなかから一定の利子をはらっている。
問6 失業について
① 失業者に関する問題を担当する国の省庁を何といいますか。
② 失業者には、あらかじめ国に支払ったお金を元手に、一定の保険金(失業保険)が支給されます。これは以下の4つの政策のうち、どの政策にあたりますか。
ア.社会保険 イ.公的扶助 ウ.社会福祉 エ.公衆衛生
③ ②の保険金の支給が終わっても仕事が見つからず、十分な財産もない場合は、生活保護の支給を受けることができます。これは以下の4つの政策のうち、どの政策にあたりますか。
ア.社会保険 イ.公的扶助 ウ.社会福祉 エ.公衆衛生
問7 これはどのようなお金のことですか。説明しなさい。
解答欄:
1.
問1① ② 問2① ②
問3 問4 問5 問6
2.
問1 問2 作る: 実行: 判断:
問3 書名: 人物名: 問4
問5 刑罰のルール: 政治のルール: 問6
問7① ② 問8 問9 問10
問11 ア. イ. ウ. エ.
問12 問13 名称: 機関:
問14① ② 問15
問16 問17 名称: 事件名:
問18 問19
問20 ア. イ. ウ. エ.
3.
問1① ② 問2
問3① ② 問4 問5
問6 問7
4.
問1①変化: 名称: ②
問2 問3 高速道: 新幹線:
問4 問5① ②
問6① ② ③ 問7
解答編
1.問1①生存権 ②エ 問2①国の借金を返すための費用 ②増加する 問3 ウ 問4 イ
問5 ODA 問6 ウ
(問1①、問2①、問5各2点×3 その他1点×5 計11点)
2.問1 主権 問2 作る:立法 実行する:行政 判断する:司法 (完答)
問3 『法の精神』、モンテスキュー 問4 ウ 問5 刑罰のルール:律 政治のルール:令
問6 ウ 問7①自由民権運動 ②イ 問8 国民主権 問9 ウ 問10 エ
問11 ア.農林水産省 イ.文部科学省 ウ.国土交通省 エ.外務省
問12 政令 問13 条約、国会 問14①議院内閣制 ②憲法の改正 問15 刑事裁判、民事裁判(完答)
問16 違憲立法審査権 問17 司法権の独立、大津事件 問18 ウ 問19 国民審査
問20 ア.社会権 イ.自由権 ウ.請求権 エ.平等権
(問4,6,7②,9,10,18各1点×6 その他2点×26 計58点)
3.問1①第四次中東戦争 ②OPEC 問2 輸出の自主規制 問3①現地生産 ②イ
問4 ウ 問5 ウ 問6 ウ 問7 エ
(問1~問3①各2点×4 その他各1点×5 計13点)
4.問1①上昇する、インフレ ②引き上げる 問2 GDP 問3 東海道新幹線、名神高速道路 問4 ウ
問5①ウ ②エ 問6① 厚生労働省 ②ア ③イ 問7 返すことができなくなった借金
(問2・3・6①・7各2点×5 その他各1点×8 計18点)
合計100点
解説:
1.
問1② 社会保障制度を担当するのは厚生労働省
問3 地方交付税交付金は、地方自治体、つまり都道府県及び市区町村に支給される。
問4 公共事業費は、不況のため21世紀初めまで増加したが、現在は国の財政を立て直すため減らされている。
問5 ODAの日本語訳は「政府開発援助」という。
2.
問4 冠位十二階(602)⇒憲法十七条(603)⇒遣隋使(607)⇒大化の改新(645)
問6 ア 石山本願寺を制圧したのは織田信長。秀吉はその跡地に大阪城を建てた。
イ 御成敗式目の制定は1232年。
エ 吉田松陰が処罰されたのは、幕末の安政の大獄(1859)のとき。
問7 国民の権利は法律で制限可能だった。
問9 天皇の国事行為に対する助言と承認を行うのは、内閣
問10 ア 衆参両院の議決が異なる場合は、両院協議会、または衆議院での再可決によって法案を成立できる。
イ 法案は、衆参のどちらから審議してもよい
ウ 憲法の改正には両院それぞれで3分の2以上ずつの賛成が必要
問14② 内閣総理大臣の選出方法は憲法で定められており( 条)、首相公選制にするには憲法改正が必要。
問18 大津事件は1891年に発生。来日中のロシア皇太子が警官に傷つけられ、政府は裁判官に被告の死刑を要求したが、裁判官はその要求に従わず、公正な判決を下したことで知られている。
3.
問3②工場の跡地の利用方法が見つからず、問題となる場合が多い。
問4 ア 社会保障の費用は税金と保険料の2つでまかなわれています。
イ 介護保険の保険料は高齢者も負担しています。
エ 生命保険、損害保険は民間の企業が販売している商品です。